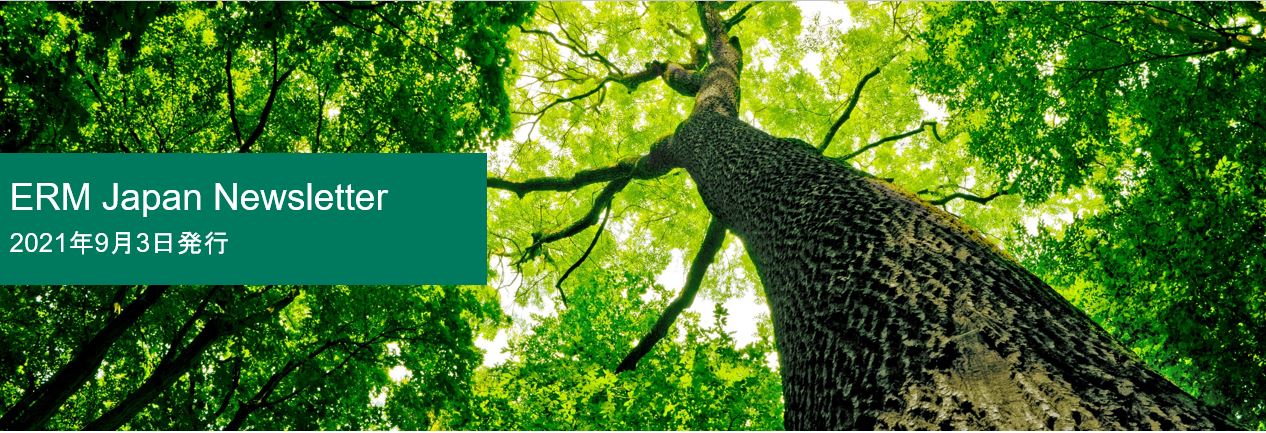土壌汚染対策法の改正動向及び事業者・土地所有者への影響
平成29(2017)年に改正された土壌汚染対策法(土対法)の施行(平成30(2018)年、または平成31(2019)年)から5年経過後の令和6(2024)年度から次の法改正を見据えた土対法の施行状況の確認・見直しが環境省にて行われています。令和7(2025)年の夏~秋ごろに環境大臣への答申の取りまとめが予定されており、作業が順調に進めば令和8(2026)年に土対法が改正される可能性があります。法の見直しの議論を行っている中央環境審議会 水環境・土壌農薬部会 土壌制度小員会では、2025年5月までに次の7つの論点が挙げられ審議されています。